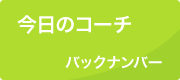第11回
2011.02.11 | 16:57

- 西尾 克幸 さん
- NTT番号情報株式会社
人事部人材育成担当課長
PHP認定ビジネスコーチ - メールマガジン
「100万人のビジネス・コーチング」
第30号掲載
今日ご紹介するのは、西尾 克幸(にしお かつゆき)さんです。
西尾さんは、努力の人です。社会人として多忙を極めながらも業務の傍ら大学・大学院で学ばれ、MBAを始め、多くの人事・人材に関する資格を取得されています。
コーチングでも、通常の講習日のほかに平日夜7時開始、ほぼ週1回というハードな勉強会に頻繁に顔を出されていました。
しかし、はたからみると“努力”とうつるところを、「自分の価値を高めるために楽しんでやる」とするところが西尾さんらしさでしょう。
今回はちょうど、ほぼ1年にわたったコーチングの学びが修了したばかりというタイミングでお会いしたこともあり、西尾さんはこの間の思いをさまざまに振り返っておられるようでした。苦しくて悩まれたこともあったようでしたが、学びで得たものを語るとき、西尾さんのお顔は笑みに輝いていました。
西尾さんは、ご自身の変化の旅を語ってくれたのでした。
西尾さんに伺いました
現在のお仕事
タウンページ、ハローページ、iタウンページならびに電話番号案内(104)の業務を取り扱うNTT番号情報株式会社に勤務しています。人事部に所属し、人材育成や人的資源開発の業務に従事しています。 また、研修講師として登壇もしています。
コーチングはいつから学び始めましたか
単発のセミナーのようなものは以前受講したものがありましたが、本格的に学ぶこととなったのは2010年からです。私自身の想いとして、コーチング元年と設定し、2010年1月よりPHPビジネスコーチ養成講座を受講し、その学びをスタートさせました。
そのきっかけは?
研修講師としてのスキルや能力を高めるため、2009年にPHP研修インストラクター養成講座を受講・修了しました。まだまだ講師としての力・スキル・幅の狭さを痛感し、研修講師として価値を高める手段が必要と考えていました。また、企業のマネジャーという立場では、育成をするというポジションでありながら、経営陣からの期待や成果を重視するあまり、部下とのコミュニケーションがうまくいっていない時期でもありました。さらに、家庭では厳格な父として長女の好奇心の目を抑制してしまっており、そんな自分を内省していました。こんな背景から、学ぶ対象を模索していました。 そんなとき、ビジネスコーチングの講座の存在を知り、きっかけになりそうだという直感を信じて申込みを行いました。
西尾さんの一言
大学院で学んだこととコーチングで学んだこととは、全部一致しているんです。それは自分にとって、すごく驚くべき発見でした。
聞き手: 斎木(fRee sTyle)
(以下会話中、敬称を省略します)
人はコントロールされたくない
- 斎木
- 今、お仕事のいろいろな場面でコーチングを活用されていると思うのですが、具体的には、いつ、どこで、誰に、どんなところでコーチングを実践されているのですか。
- 西尾
- 一番近しいところで言えば、会社の中で部下とのかかわりですかね。
また私は、ES、従業員満足度を高める取り組みをしているのですが、その中で講師というか、ファシリテーターをしているとき、使うことが結構多いですね。
そのほかの場面でも使うのですが、いつも使っているかっていうとそうでなくて、「今使うときだな」ってスイッチを押す、ということを意識してやっています。 - 斎木
- 戦略的ですね(笑)。
- 西尾
- 戦略的です(笑)。
- 斎木
- 特に講師のときは、どんなときそのスイッチが押されるんですか。
- 西尾
- そうですねえ…。
簡単に言うと、受講生が答えを求めてくるんですね。それは、こっちが答えをもっていると思っているから。
でもそこは、「自分の中でどう思ってる?」「どうしたらいいと思う?」とか、まあ、コーチング的アプローチをしています。 - 斎木
- それはセミナー中?
それとも休み時間で1対1とか? - 西尾
- どちらもあります。
あと、「どう考える?」と聞いたとき、「それが分からないんです」っていう答えだと、周りに「どう? これについて誰か意見ない?」とか「今みんな、どこに行こうと思ってるんだっけ?」とゴールやアウトカムを意識させることとかもします。 - 斎木
- なるほど、ファシリテーションが混じっているんですね。
受講者に答えを求められたとき、「答えを導き出す」ということでしょうか。 - 西尾
- はい。コーチングを学んでいる中で出てきたと思うんですが、「人間はコントロールされたくない。自分でコントロールしたいんだ」って。
やっぱり、こっちが答えを言っちゃだめなんですよね。それだとやらない。
結局、人は自分で選択してやるんですよね。
人間力を高めたい
- 西尾
- 実は、仕事の話なんですが、コーチングを始める前ごろ、役員からの期待がすごく大きかったんですね。
今考えると、プレッシャーになっていたのかもしれないけど、マネージャーだったこともあって、「とにかく成果出さなきゃ」って思ってたんですよ。なので、部下に対しても「引き出す」というよりは、「これやるんだろ、向かうんだろ」って、もう無理やりでもぐいぐい引っ張っていく、って感じだったんです。だからうまくいかなかった。
コーチングを学んで「ともに勝つ」ってことが、今ようやく分かるようになってきた気がするんですよ。 - 斎木
- そうなんですか…。
- 西尾
- 特にベーシックのとき(PHPの養成講座では、半年のベーシックコースとその後4カ月のアドバンスコースがある)は、ほんとにテクニックに目が行って「なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ」ってばかり思ってましたね。
それも今思うと、コーチングを「マネージャーという役割の中で成果を生み出すためのツールの一つ」って考えていたからかもしれません。 - 斎木
- それが変わって行ったんですね。
- 西尾
- アドバンスのころからですかねえ。だんだん「ともに勝つ」っていうふうになったのは…。
やっぱり、それまで人へのアプローチの仕方で、行き詰まることが多かったんですよね。 - 斎木
- 講師のときとかも?
- 西尾
- そうです。
例えば、さっきみたいに答えを求められたときは、私が答えを返してたんですよ。 - 斎木
- じゃ、全然違ってたんですね。
- 西尾
- だから、こちらが一所懸命勉強しなきゃいけなかった。
- 斎木
- あ、なるほど。
- 西尾
- そういう相手には一応、「聞いてくるって、それ依存だよね」って指摘はしてたんですよ。
すると、相手も答えを出してくるじゃないですか。でも、私も答えをもってるんですよ、そうは言いつつ。で、相手の答えに対して、「こうじゃないの」ってまた答えを示しちゃうんですよね。 - 斎木
- ふーん…。
- 西尾
- それで、やんわり反発されたりとかもあって。
相手にすれば、「コントロールしようとしてる」と感じちゃったんでしょうね。そういうフィードバックを受けて、自分でも「なんか、これ違うな」という違和感があり、「新しいアプローチをもっと知りたい、人間としても幅を広げたい」って気持ちが起こったんですよ。
このことが、コーチングを学ぶことの源泉になっているのかなと。 - 斎木
- その違和感というのは、自分の人間的なこととかかわってるという気がしたんですね。
- 西尾
- 「きっかけ」にも書いたように、コーチングの勉強の前に受講したPHPの研修インストラクタ―養成講座で、講師として技術的なこともさることながら、人間性、人としてどうあるべきかが大事だって何度も言われて。
すごく背筋が伸びたというか、それであらためて、自分の人となりを考えることができたんです。幸い、講座では修了時に良い評価をいただいたんですが、正直、自分としては「まだまだ全然足んないな」って思ったんですよね。 - 斎木
- それは、西尾さんが目指している人間的な幅とかの面で?
- 西尾
- はい。
「ここで終っちゃだめだな、このまんまじゃ、とても満足できる状況じゃないな」って痛切に感じたんですよ。
それで、「もっと人間性を高めたい、そこをもっと磨きたい」って気持ちで、PHPのビジネスコーチを学ぶことにしたんです。
アハ体験!
- 斎木
- コーチングを学ぶまでにいろいろな想いがあったんですね。
あらためてコーチングを学ぶ前と後ではどういったところが変化したと思われますか。 - 西尾
- そうですね…。
「肯定的意図が誰にもある」ってことが、強く印象に残ってますね。
マイナスの行動にも肯定的意図があるっていうのは、すごく納得感があったんですよ。だから、「その人にラベルを貼るべきではないな」とも思いました。
今まではやっぱりラベルを貼ってたんですよ。「この人はこんな人」とか。いろんな事前情報を聞くと。 - 斎木
- 先入観でね。
- 西尾
- はい。でもそうじゃない。
そういうふうに思うと、今までの見方が変わって行きましたね。 - 斎木
- そういう変化があったんですね。
そのほかには? - 西尾
- やっぱり視点のことですけれど、「俯瞰的に見る」ということですかね。
- 斎木
- 第3者的立場で客観的に見る、メタポジションからの視点でしょうか。
- 西尾
- そう、メタ!
- 斎木
- 「メタは印象が強い」っておっしゃる方が多いですよね。
まさにコーチングらしい考え方、ものの見方だと思いますね。 - 西尾
- 以前は、議論をしていてもその話題の中に入っていってしまって、さらにそれを自分でもってきちゃうようなことがあったりしたんですけど、今は一歩引いて客観的に見ることができるから、議論全体をいい方向にもって行ける。もちろん参加者全員の納得感も得ながら。そういうことができるようになったと思います。
これは実際にやってみて、アハ体験じゃないですけど(笑)。議論を進める中で、メタの視点を使うことによって気づきが多く生まれますね。 - 斎木
- 西尾さんのように、日常的にファシリテーターの役割が多いと特にそう感じる機会が多いでしょうね。
- 西尾
- そう、多いですね。
あと、視点ってことで言えば、この動き(手を上下させる)っていうのには驚きました。 - 斎木
- ああ、物事の論理のレベルをさまざまに変えて見ていくという考え方、チャンキング(21号参照)でしょうか。
- 西尾
- そうそう。「具体的に言うとそれどういうこと?」っていう詳細情報から、「全体的に見るとどんなことが言えますか」という全体情報まで、こんなふうに(手を上下させる)エレべータ―的にものを見ることができるってことを学んだのは大きかったですね。
- 斎木
- なるほど、エレベーターね(笑)。
詳細情報から、ぐっと上に上がって俯瞰的に見る全体情報まで、視点を上げ下げして物事を考えることができますものね。この行き来のことですね。 - 西尾
- そうです。
初めは、チャンクという言葉も、そういう動かし方があることも知らなかった。だから、問題をなんとかしたいなと思っても、できなかったんです。
それがエレベーターってものがあって、それを上下したり、また横に動かすチャンクラテラリーもできるって分かり、さらにそのエレベーターを自分がコントロールすることができる、そういう感じでしょうか。 - 斎木
- まさにアハ!ですね(笑)。
すごく嬉しかった…
- 斎木
- では、最近特にコーチングが機能したっていう体験を教えてください。
- 西尾
- えーと、三つ…ですかね。
一つは会社のことで、プロジェクトの事務局を手伝ってくれている女性がいるんです。
彼女は近年すごくリーダーシップを発揮するようになってきたのですが、がんばっている自分がみんなの中で浮いている、孤立をしてモチベーションが上がらない。「もうやれない、無理です」と相談を受けたんです。
で、「ちょっと飯食いに行こうか」と、飯食いながらコーチングしたんですよ。コーチングのモデルの一つを使って、その中にはメタの視点も入れて。
そしたら、「私がここで悩んでいることって、ほんとに小さなことだったのね」って言ったんですよ。「なんて小さい自分がいたんだろう」って。時間的には20分くらいだったんですけど。 - 斎木
- 20分でねえ…。
- 西尾
- 「すごくすっきりした」って、顔が明るくなっていました。
あと、目線が下がってたのが上に上がって、最後は、「がんばろうと思います。やります、私」って。 - 斎木
- すばらしいですねえ。
- 西尾
- 短い時間でマイナスがプラスに転じ、モチベーションを変えることができるという体験でした。
実はそれまで、コーチングがこんなに機能したってことがなかったんですよ。話す前と終わった後の顔付きが全く違うという状況は初めてで、「こんなに違うものなんだ」と驚きました。 - 斎木
- それは嬉しいですよね。
また、クライアントの顔つきや振る舞いは、本当にいいフィードバックですよね。 - 西尾
- ええ、本当に。
それから、二つ目は元部下です。
彼女は私の部署の一番若い部下だったんですが、専門知識が充実していることから重宝して「あれやって、これやって」と仕事を頼み、彼女も一所懸命答えてくれるという信頼関係があったんです。それが、チーム全体のバランスのこととかがあって私が接し方を変えたことで、彼女も面白くなくなったんでしょう、全然こちらの言うことを聞かなくなってきた。
ちょうどそのころ、コーチングの勉強を始めていたので、彼女にもやってみたのですが、全く機能しなかったですね。ほんとに全く。 - 斎木
- 悩まれたんですね、西尾さんも。
- 西尾
- うーん…ちょっと苦しかったですね。
結局彼女は退職しました。でも、それから1カ月ぐらいたったとき、連絡が来たんですよ。 - 斎木
- え、あちらから、あなたに?
- 西尾
- ええ。
その1カ月で彼女もいろいろ考えたみたいで。
それで「転職活動をして、内定を何社かからいただいたけれど、どこに自分が進もうとしてるのか分からない」と。
もう利害関係もないですし、フラットな自分になってアプローチしてみようかと会って話をしました。
で、コーチングをして、彼女は「良かったです。スッキリしました」って帰って行ったんですね。 - 斎木
- へー!
- 西尾
- 実はそのとき、自分の中であまり手ごたえがなかったんですよ。
でも、そのあと、「会社を決めました。コーチングのおかげです。ありがとうございました。またお願いします」ってお礼のメールが来たんですよ。 - 斎木
- 嬉しいことですよねえ…。
- 西尾
- はい。
いいか悪いか分からないですけど、彼女の人生において、一つのきっかけになることができたってことは、自分にとってはすごく嬉しい体験でしたね。それが二つ目。
もう一つは子どものことです。
私、女の子が2人いるんですが、上の小学校2年生の子です。 - 斎木
- あ、まだお小さいのね。
- 西尾
- はい。その子に対する私のアプローチも結構きつかったんですね。
それで、彼女は引っ込み思案な子どもになっちゃって、それで、自分のアプローチを意識して変えていったんです。
それから彼女、結構チャレンジするようになってきました。さらに、コーチングというものに触れて、子どもへのアプローチも大きく変わったんですが、決定的なことがありまして。
去年の秋ごろだったか、彼女が私に相談しに来たんですね。朝の時間、皆で歌を歌うんだって。それが嫌でしようがないと。 - 斎木
- (笑)可愛いですねえ。
- 西尾
- ええ(笑)。
それで「なんで?」「現状どうなの?」「原因なんなの」って聞いて。
そしたら、「歌の意味が分かんない」って言うんですよ。歌詞も、なぜ歌うのかも。
「じゃ、どうあったらいいの?」ってアウトカムの話をしたら、「みんなで楽しく歌いたい」。 - 斎木
- 「ともに勝つ」っていうお父さんのお子さんですね(笑)。
- 西尾
- (笑)
「そうだね。じゃあ、そのためにできる方法ってある?」って聞いたら、子どもってすごいなあって思ったのは、ポンポン出てくるんですよね。ほんとね、ものの7分くらいのコーチングでポンポン出てきて。「歌詞の意味、分かるようになること」とか「それちょっと勉強してみる」とか「『みんなで歌うと楽しいよ』って働きかけてみる」とか。
「そっか、できそう?」って聞いたら、「うん、やるやる、明日からやる!」って。 - 斎木
- いやー、すごいすごい。
- 西尾
- で、次の日聞いたんですよ、「どうだった?」。
「うん、やったあ」って。「すごいよかった、楽しかったあ」って。
これ、すごく嬉しかったです。 - 斎木
- ですよねえ。
あの、「ポンポン出てきてすごいなあ」っておっしゃったけど、そういう雰囲気をお父様がつくったんでしょうね。 - 西尾
- ああ、そうかもしれないですねえ…。
初めて意識してコーチングしたんですよ、家族に対して。「家族にコーチングしちゃいけないのかな」って、勝手に思ってたんですけど。 - 斎木
- 肉親はやりづらいって言いますしね。
- 西尾
- そう言いますよね。
でもやってみたら、良かったんですよ。
だから、嬉しかったですねえ…。
フラットであることの大切さ
- 斎木
- 今三つ、ちょっとずつ場面が違いますが、なにがうまく行った要因だと思いますか?
- 西尾
- 「引き出そう」ってところに意識を向けてるからかな。
- 斎木
- 何を引き出そうとしてるんですか?
- 西尾
- 相手の中にある、こう、もやっとしたもの。
- 斎木
- もやっとしたものね(笑)。
- 西尾
- そう(笑)。
答えの周りにあるオブラートが重なって見えないものに意識を向けてるからだと思います。
それから、私の意見、私利、私欲は一切出さないってことは、意識してるっていうか、それは共通してやってないんですね。 - 斎木
- それが共通点。
さっきフラットって言っていたけど、それが意識したこと? - 西尾
- 意識したというか、しなくてもできた…。
私の中に答えをもたずに、自分の中は真っ白にしてアプローチをする。自分が今もっているスキルだったり、アプローチの方法で最善を尽くす、ということに意識を向けたんですね。 - 斎木
- そこを大事にしながら接したということですね。
- 西尾
- 勉強会のとき、素の自分として今もってるものでできることをやったら、「いいね」ってフィードバックを受けたんです。
そのときの気持ちはフラットで静かなんですよ。静かな穏やかな波みたいな状態。そういう状態でコーチングに入っていくことって大事なんだなあって思いました。
また、私の中の波が激しかったりすると、相手にとっては受け入れられないと思います。穏やかでいるからこそ、相手の心の動きに対応できる。
これまでは、相手が「大変なんですよ」って言うと「大変なんだよねえ!」ってよく一緒に激しく波立っちゃったんですよね。それで、「なんか違うな」って違和感がずっとあったんです。
逆にフラットでいることによって、相手の感情に合わせることができるし、戻ってくることもできるって思います。
We are the world へ
- 斎木
- では、西尾さんがコーチとして大事だな、と思っていることは?
- 西尾
- 今言ったことと同じかな、と思うんですけど「すべてを受け止める力」。
- 斎木
- もうちょっと詳しく教えてください。
- 西尾
- 学びの後半、アドバンスのとき言われたんですけど、私のコーチングが「安心感とか安定感があるね」って。
嬉しかったんですが、やはり「この人に言って大丈夫だ」っていうものがコーチは大切で、それはなにかというと、受け止める力があるかどうかということだと思います。それは単にコーチングの技術があれば大丈夫ってことじゃなくて、人間としての度量だったり、魅力ある人間かどうかということだったり、その人間を信用できるかに尽きるのではないかと。
そういう人としても基本的な部分っていうところを磨くのがすごく大事なんだと思います。 - 斎木
- それは、西尾さんがコーチングを学ぼうとしたきっかけにもかかわってきますね。
- 西尾
- そうですね。
- 斎木
- あらためて、なぜそういう人間的な度量がコーチングにおいて大事だと思うんです?
- 西尾
- うーん…相手が素の自分が出せるからじゃないかな、と思います。
素のところ、本当のその人にアプローチできないと、真の問題解決はできない。
でも、その核の部分に至る前に、相手は「この人、相談できる人なのか、素を出して大丈夫な、信用できる人なのか」って思いますよね。そういう深い深いところにアプローチするのが、コーチングなのかなあって想いがあります。
あと付け加えるとすると、可能性を信じることですね。
この人の可能性は無限大だと信じて、絶対できるってところに連れてってあげる。「連れていってあげる」っていう言い方は適切でないかもしれませんが、たとえで言うと悩んだりすることは、結局狭い世界でものを見ている。それを一言で言うと、It's a small world。 - 斎木
- (笑)
- 西尾
- (笑)そこから、もっと大きい世界、俯瞰的に見れるところに世界観を変えていく。これが We are the world(笑)。
客観的に2人で見ていって、「あ、ここにいたよね、これから一緒にあそこに行けるよね」とそういう気持ちをもって実行できるのがコーチなんだなって思います。
すべて一致していた
- 斎木
- We are the world にも通じるかもしれませんが、西尾さんがコーチングを通じて社会で実現したいことは?
- 西尾
- はい、明確です、私。
“日本を変える”ってことです。 - 斎木
- でっかいですねえ。
- 西尾
- 大風呂敷ですね(笑)。
- 斎木
- いや、どんな風呂敷でもヒョウ柄でもいいけれど、どんなふうに変えたいんですか
- 西尾
- それは、日本型のリーダーシップを確立したいということです。
日本人って主体性が弱くて、受け身で、恥の文化をもっていて、リーダーシップ教育もされてないです。
日本人の可能性って、もっともっとあると思うんです。もっとプラスの動き、行動がいっぱい出てくると、世界でさらにいろんなことができるんじゃないかなって。そういう可能性にアプローチして、もっと引き出してあげたい。プラスの動きの人がいっぱい出てくればいい。だから、日本型リーダーシップの確立なんです。
リーダーシップって基本的に欧米から入ってきて、輸入型なんです。それを日本人がまねしようと思っても、うまくできないわけだし。 - 斎木
- その日本型リーダーシップをもっている人は、どんなことを備えてるんですか?
- 西尾
- これはまだ研究の途中なんですけど、いま変革型リーダーシップっていうのが、欧米ではいいって言われているんですね。
それが日本にも入ってきているんですけど、私が研究しているのは“支援型リーダーシップ”なんですよ。 - 斎木
- 支援型。
- 西尾
- そう、人の成長を支援したりとか、まさにコーチングとかとすごく合致するんです。
それがあると、要はみんな、自分からやろう、やってみようってことを信じられる。そこにサポートできるということになるのかな、と思うんですよ。 - 斎木
- 今まで西尾さんがやってきたことと一致してますね。
- 西尾
- そうなんです。
一致してるんですね、大学院で学んだこともコーチングで学んだことも。
それは自分にとって、すごく驚くべき発見でした。
すでにあなたは進んでいる
- 斎木
- これからコーチングを受けたいと思っている人に、一言お願いしたいんですが。
- 西尾
- その人たちは、「何か変えたい」とか「立ち止まっていることがもどかしい」と考えてコーチングに来るわけですよね。その時点で、すでに進んでるんだ、と思います。
- 斎木
- 一歩進んでるんだ、と。
- 西尾
- そう。私が研修をやっている中で、一番最後のセッションで必ず入れているのが“踏み出す”なんですよ。
「いや、よかったね、今日の研修」とか、「よかった、今日のコーチング」とか、「楽しかったです」じゃだめなんですね。行動しなきゃ。一歩踏み出さないと。
その一歩踏み出してることを、やっぱり肯定したい。
「あなたがここに来てること自体がすでにあなた自身を変えていることだし、一歩踏み出していることは素晴らしい」と言いたいです。 - 斎木
- それを聞いただけで元気が出そうですね。
- 西尾
- あと、私もそうだったんですけど、悩んでる人、コーチングを受けたいなって思ってる人って、孤独だと感じていると思うんです。
でも、孤独じゃないんですよね。孤独と思い込んでいるだけだと思います。 - 斎木
- 思い込んでいるだけ…。
- 西尾
- コーチがいるじゃないですか。
「一緒にあなたの可能性探してみましょうよ」って。 - 斎木
- そうね、そう思ってるかも。
あと、1人でやろうと思ってるとか。 - 西尾
- あ、そうですね。
「あなたの可能性はあなたが踏み出すことでも見つかるし、コーチと一緒に見つけることもできるよ」って言いたいですね。
濃い色で塗りつぶされた1年
- 斎木
- では、これからコーチングを勉強しようと思ってる人へ一言。
- 西尾
- これはもう、私がすごい悩んでたときに、「もうだめだな」って思ってたときに…。
- 斎木
- 「だめだな」って思ってたのね(笑)
- 西尾
- 思ってたんですよ、何回も(笑)。
ベーシック学んで中間ごろ、「向いてないな、もう辞めたほうがいい」って思って、自己嫌悪に陥ることが何回もあって…。一所懸命やってるんだけど、機能しなかったからなんですが、そのとき「コーチングって万能じゃないんだよ」っていう言葉に救われた。 - 斎木
- ビジネスの場では、例えばときにはティーチングが必要、というときもありますからね。
- 西尾
- はい。万能じゃない。
だけど、有効なんです。それは確実に言えます。
あとは、「人間として成長できる」ということですね。
それは自分でも感じますし、それによってコミュニケーションも一緒に変わるんだと思います。
学んでいるときは、正直大変です。ほんとに大変ですけど、やってよかったと思います。それは達成感とか満足感とかじゃないんです。そういうものを超えて、単純に相手の笑顔とかを見ることができたのが一番よかったかなと思うことです。そういうふうに思えるようになったんだな、自分も、と、ちょっと感慨深いですね…。
今まで大学でも大学院でも学んだし、いろんな学びがあった中で、心の動きが一番あった学びでしたねえ、コーチングは。
先に言った「ともに勝つ」も、受講する前は「ともに勝つ、ともに成長する」とか言っておきながら、実は「勝たせてやる」だったかな。だけどそれじゃだめで、「一緒に勝とうぜ。勝てるよ。大丈夫、勝てるはずだよ、絶対に」というふうに変わった。そこがまた大きかったかなと思いますね。 - 斎木
- 濃い体験でしたね。
たった1年の学びなんだけど。 - 西尾
- ほんとに2010年は、人生の中でも濃い色で塗りつぶされている1年、忘れられない1年ですね。
- 斎木
- 今年はまた、どんな色が塗られる年になるか楽しみですね。
ぜひ素敵な色にしてください。
今日はどうもありがとうございました。