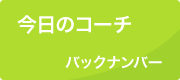第5回
2009.07.15 | 04:00
- 中野 達也 さん
- ピップトウキョウ株式会社
経営企画部所属
PHP認定ビジネスコーチ
日本キャリア開発協会認定キャリア・ディベロップメント・アドバイザー
米国NLP協会認定マスタープラクティショナー - メールマガジン
「100万人のビジネス・コーチング」
第12号掲載
今日ご紹介するのは・・・小さな子供からお年寄りまで、誰もが知っている「ピップエレキバン」、そして「ピップマグネループ」、「スリムウォーク」など数々のヒット商品で有名な、ピップトウキョウで活躍中のこの方です!
中野さんはピップトウキョウで、長年採用教育課に所属し、社員の採用・研修を担当し、研修講師としても7年間のキャリアをお持ちです。また、社外の大手ビールメーカーをはじめ、ドラッグストアやホームセンターなど小売業において、講師を務められたご経験もあります。昨年の11月から経営企画部の配属となり、ますますその活躍ぶりが期待される中野さんです。
中野さんの魅力は、何よりもそのバイタリティ。興味のあることには何にでもチャレンジし、そして日々起こる様々な事柄を、チャンスとして捉えて精力的に取り組んでいく、そんな意欲的な方です。
その一方で中野さんは本当に謙虚で、言動も穏やか、頼りがいがあるのに、とてもフレンドリーです。
情熱的、意欲的でありながらも常に心の平静を保ち、日々前進し続ける中野さんのインタビューをどうぞお読みください。
中野さんの一言
コーチのステイトがいい状態でないと、
人は支援できない
聞き手: 城田(fRee sTyle)
(以下会話中、敬称を省略します)
- 城田
- まずインタビューの第1問目は・・・、
中野さんがどんなところでコーチングを使っていたり、役立てたりしているのか、教えてください。 - 中野
- 基本的にはですね・・・使っている場所は、会社の中が多いですね。
それは、部下との打ち合わせやミーティング、あるいは人事関係の面接や目標設定面談であったり・・・
あるいは・・・そうですね・・・これは、たまにあることなんですけれど、友達から雑談の中で相談事があったりして。例えば思春期の子供を持つ友達と話していると、すごく「こう言う風に思うんだよ」ってどっちかと言うと否定的な目で、子供を見ていたりすることがあるんですけど。そんなときに、「観方を変えてみたら、どういうふうに見えるんだろうね」なんて言うと、視点が変わってもやもやしていたことが解消されて「言ってよかったな」って言われれることがありますね。 - 城田
- それは嬉しいですね。
- 中野
- ええ。
あとは、最近子供と会話するときに、少し、使ったりしていますね。 - 城田
- お子さんとのコミュニケーションに活用できるっていう人、結構多いですね。
- 中野
- そうですね。
あの、柴田さんのインタビュー(注:「100万人のビジネスコーチング」第6号)のときの例みたいに、あんなに明確に変化したっていうことではないんですけれど・・・ - 城田
- うん・・・もっと日常の・・・?
- 中野
- ええ。
私が仕事を結構朝早くから夜遅くまでやっているので、会話する時間っていうのが少ないんですよね。ですから、親が一方的に話すよりも、質問をして、話をしてもらおうと・・・会話の量を増やす、という意味で。
「今日はどうだったの?」って訊くだけですけどね。 - 城田
- いいですねぇ~、すごく!!
- 中野
- スキルというか、会話ですね(笑)
- 城田
- いやぁ、今のはちょっと、全国の親御さんたちに聞かせたい。
たしかに毎日時間がないってお父さん、お母さんは思っているかもしれないんですけれど・・・。 - 中野
- そうですね。
- 城田
- でも、だからこそ、自分が話すのではなく、子供に話させる時間を増やすっていうんですね。それってすごく、すごいいいお父さん・・・!
- 中野
- いえいえ(笑)
それに会話がもしなかったら、子供も「(親が)関心がないんじゃないか」って、そう思われるの、僕いやなんですよ。
親としてはちょっと、落胆しますね。 - 城田
- そうですね。
悲しいですよね、子供にそんな風に思われたら。 - 中野
- だからできるだけ「関心を持って見ているよ」とか、あるいは「君の今やっていることをすごく気にしているよ」とか、「成長を願っているよ」っていう意味をこめて、会話の量を増やしたりしています。
- 城田
- 家庭で、コーチングのスキルというか、考え方のようなものが、役に立っているんですね。
- 中野
- そう思いますね。
- 城田
- お子さんの反応はどうですか?
- 中野
- 今、中2の男なんで・・・
- 城田
- じゃあ、結構難しい時期・・・?
- 中野
- 基本はあまり話さないっていう方向なんでしょうね、中2の男としては・・・
でもね、まあ・・・どっちかっていうと男の子にしては話す方だと思いますね。それに聞けば話しますし。
で・・・特に今、剣道をやっていて。 - 城田
- へえ。。。
- 中野
- ちょうど今、勉強や剣道などで知識とか技術とかがちょうど成長にさしかかろうとしているところで・・・
ですから、できるだけ聴いて、モチベーションがあがるように承認してあげて・・・そういうところを心がけてやっていますね。 - 城田
- わぁ、本当にいいお父さんですね。
そんなお父さんだったら、いいですよね。 - 中野
- でも、いつもそういうことができるわけじゃなくて・・・
仕事のことで頭がいっぱいになっていて、もう家帰って、ただぼーっと映像だけ、テレビを眺めていたいっていうときは、話しかけられても「ふん、ふん」って言っているときもありますよ(笑) - 城田
- そうですよね。
24時間いつでもっていうわけにはいかないですよね。
家庭ですものね。自分が羽を伸ばすところでもあるし。 - 中野
- そう言う意味では、コーチ、という役割や立場から見て、コーチの状態、感情の状態がですね、ステイト(注:心的状態)が、いい状態でないと、やっぱり人は支援できないなってよく思いますね。
- 城田
- なるほど・・・
自分がよい状態でないと、人を支援するのは、難しいんですね。 - 中野
- 難しいですね。
- 城田
- いいステイトを作って、ということですね。
- 中野
- はい。
- 城田
- なるほどね。
あとは、家庭以外でも、コーチングを使っていることはありますか? - 中野
- ええ・・・
部下の仕事に対するモチベーションを向上させるという意図で、職場では、できるだけ、考えさせるようにしようと思っていますね・・・
私が「こうやってね」って言えば、その通りにできることは確かだと思うんですけど、それは私のアイディアで、あるいは発想、考えであって、アイディアのひとつだと思うんですよね、それは。
ではなくて、仕事はある意味、課とか部のメンバー全員で、ある目標を達成しようというものだから・・・たとえば、メンバーが3人いれば、3人のいろんなアイディアを出して、その中で一番いいもの、あるいはメンバーのアイディアを付け加えていいものをやっていった方がいい・・・そういう考えなんですね。 - 城田
- じゃあ、アイディアは複数あったほうがいいんですね。
- 中野
- ええ、複数あった方がいいし、それぞれのアイディアを足しこんでいって、それで、もっともいいアイディアや考えを使って進んでいったらいいと思っているので。
そのときに「あなたはどう思ってる?」「あなたはどう考えるの?」ってメンバーに訊くことで、アイディアを出してほしいと思っているんですよ。
だからそのときにあえて質問をしていく・・・「君はどう思うの?」って。
で、できたらそのアイディアを、自分の考えとあまり違わなかったら、その人のアイディアでやらせようと思っているんです。 - 城田
- あぁ・・・なるべく崩さないっていうか。
- 中野
- そう、崩さないで。
- 城田
- それは、どうして?
- 中野
- その人のアイディアは、その人が出してきたアイディアなんで、固有の・・・自分のもの、じゃないですか。そのものを使って、やらせてあげたいんですよ。それはモチベーションにつながると思うんですね。
- 城田
- そうですね。
- 中野
- そこを、上司の意見で変えられた、とかあるいは、変ってしまったとか・・・っていったときに、やる方の、部下の、モチベーションってさがってしまうんじゃないかなって気がしているんで・・・できるだけその人のアイディアを尊重して。
何か付け加えたり、削ったりする場合でも、もう一回質問してみる・・・「こういった観点からはこのアイディアはどうだろう?」で、本人がアイディアの変更を決めたんだ、っていうことを認識させたうえで、やってもらうように、そういったように、できるだけしているんですよね。 - 城田
- いいなぁ。理想的ですよね。
上司から「あなたはどう思うの?」って訊かれたら、すごく嬉しいですよね。
しかもそのアイディアをできるだけ、尊重しようとしている中野さんの気持ちは、たとえ言葉に表れていなかったとしても、それはどこかに表れていますよね、きっと。 - 中野
- 根底にあるのは、私自身「私のアイディアでやらせて」っていうのがあるんですよね。
- 城田
- みんな、そうですよね。
- 中野
- 割と、今までの上司が、そう言う風に自由に、自分の発想とかを使ってやらせてくれた人たちが、多かったっていうこともありますね。
- 城田
- じゃあ、上司に恵まれてきたんですね。
- 中野
- 恵まれて来たんですね。
それで成果を創ってきたっていう体験もあるので。それは自分がやりやすかったので、部下にもやりやすいようにしてあげたいなって、そういう面があって、やっているんですけどね。 - 城田
- う~ん・・・素晴らしい。
- 中野
- いつもそうじゃないんですよ(笑)
できるだけそういう方向で考えているってことですね。 - 城田
- そうよね。なかなかできないですよね。一回もできない人だっているんですものね。
- 中野
- ただ部下の状況、つまり習得状況をしっかり判断する必要はありますね。
技能とか知識とか意欲がまだ低い、教えなきゃなんない人には、ある程度「こういう方向でやってね」って言いながら、少し状況を見ながら。 - 城田
- さすが、コーチングの習得者ですね。部下の開発レベルに合わせてる(笑)
部下への補助の度合いを、そのさじ加減を、状況を見ながら決めるって上司の大切な役目ですよね。 - 中野
- そうですね。
実は僕ね、失敗したことがあるんですよ~。 - 城田
- え、失敗?
- 中野
- うん・・・
あの、もともとは、その・・・自分のマネジメントのタイプを言うと、委任型、なんですよ。 - 城田
- あぁ・・・任せるタイプ?
いいじゃない? - 中野
- ええ。任せるタイプなんですよ。
そしていつも使っている自分のスタイルは使いやすいじゃないですか、その委任型っていうのは。 - 城田
- ああ、自分の得意なスタイルですものね。
- 中野
- ええ。
で、誰にでも委任型で、やってたんですよ。
だから頼んだ仕事について、その人に委任じゃだめなのに、委任型でやっていたために、その彼は、考えあぐねちゃって、できないでいたわけですよ。それを「何でできないんだ?」って言っても、できるわけ、ないですよね。 - 中野
- そうですよね。
まだ、ノウハウとか経験とか、不十分なんですものね。 - 城田
- そうなんです。だから部下が悪いんじゃなくて、俺が悪かったんだな・・・って(笑)
そういう体験を、何人かの部下とのやり取りの中でしてきて、「ああ、やっぱり、相手の開発レベルに合わせてやらないと、本当にダメなんだな」って思って・・・それがあったからこそ、ですね。 - 城田
- 本当にそうですよね!
任せりゃいいかって言ったら、そうとは限らないんですものね!
補助輪がまだ必要な人には、徐々にはずしていかないとうまくいかないっていうことですね。 - 中野
- そうです。
- 城田
- コーチングはいろいろなところで、中野さんの役に立っているんですね。
ところでコーチングを始めたのはいつでしたっけ? - 中野
- 確認してきたんですよ(笑)。いつからだっけな・・・って。
結構経ってますね。本格的に学び始めたのは、2004年の4月に、PHPビジネスコーチ養成講座のベーシック第5期にいったときからです。 - 城田
- 結構、前、じゃないですか?
5年くらい前・・・? - 中野
- はい。
で、その1年位前に、あるところで、1日コースを受けてて、そこで学んだことを使って、会社の中で、係長研修の中でやってみて、それをそのときの上司が見ていて、「これ、会社の管理職クラスに必要だね」って言って、「本格的に学ぶところがあるんだったら、行ってきたらどうか?」っていうことがあったんですよ。 - 城田
- いい上司ですね。
- 中野
- そうなんですよ。
- 城田
- そうやって、いいものを採り入れようって。
- 中野
- そう、そう。
もう・・・定年間際の上司だったんですけど、結構理解があって。 - 城田
- へえぇ。。
- 中野
- それで、コーチ21とPHPの両方を見比べて。で、PHPの方がビジネス・コーチだったので・・・
- 城田
- ああ・・・そうですね。
講座のタイトルそのものに「ビジネス」ってはいっていますものね。 - 中野
- ええ。で実際にPHPに行って、そのとき田近さんがデモンストレーションをしていて・・・30分位説明会で話をしてくれて、「うん、この人がいい」って(笑)。
ビジネスで使うコーチングなので、この方がいいかなっていうことで。 - 城田
- なるほど。
田近さんのコーチングはとてもビジネスに適していますものね。 - 中野
- ええ。
それで2004年の4月にベーシック・コースに行って、コーチングを始めたんです。 - 城田
- そして、養成講座だから半年間、通ったわけですね。
- 中野
- はい。
- 城田
- で、その後さらにアドバンスコース?
- 中野
- ええ、その後ね、そのベーシックの2年後に行っているんですよ。
- 城田
- じゃあ、ベーシックからアドバンスへは少し間があいているんですね。
- 中野
- そうです。
- 城田
- 様々ですよね。
ベーシック・コースのあとすぐに、アドバンス・コースに行く人もいれば、何年かおいてから行く人もいますものね。 - 中野
- そうですね。
私がベーシック・コースに行ってた頃って、ちょうど中小企業診断士の勉強を一緒にやっていて・・・ - 城田
- ああ・・・難しいですよね。あれ。
- 中野
- そうなんです。すごく大変だったんですよ。
それでベーシック・コースの後はしばらく、中小企業診断士の方だけ勉強していて、その後、いったん区切りをつけて、それでアドバンスに行ったんです。 - 城田
- あ~、そうだったんですね。
ちょっとふたついっぺんには難しいですよね。 - 中野
- ええ。きびしかった。
- 城田
- さて、コーチングを始めたのは5年前、そしてベーシック、2年ほど経って、アドバンスを3か月くらいですね。
ひととおり受講し終わって・・・始める前と後とで、何が変化しました? - 中野
- これが、今回一番難しい質問だったんですけど・・・
なぜかって言うと、もうしばらく変わった自分でいるから・・・ - 城田
- あぁ、コーチングを学んだことで、自分が変わったのは結構昔の話なんですね。
- 中野
- そうなんです。結構昔の話なんですよね。
で・・・どうだったのかなって。 - 城田
- どう変わったんでしょうね。。。
- 中野
- ええ・・・
で、考えてみたら、まず、ひとつは自分自身の変化があって・・・そして管理職者にコーチング研修をやった結果として、その管理職者の変化もあっただろうなって思うし。
私の周りの変化もあったと思うんですが。
それで、まず自分の変化としては、自分の考え方っていうのが、チャンクが大きいところから、だんだんと下ろしていくっていうロジック的な考え方を、するようになりました。最近よく言われるのは、「中野さんと話をすると、まず、でかいところから話が来るよね」って。 - 城田
- 中野さん、チャンク、大きいんですねぇ(笑)
- 中野
- そう。ビッグチャンカー(笑)
「ここから・・・ずれなきゃ、枠組みから外れなきゃ、具体的なことはいいんじゃない?」っていう感じですね。
その中で考えて、だったらこうだよね、こうだよねってチャンクダウンして考えたり・・・逆もまたあるんですよ。
すごいちっちゃなところで話しているときに、「それってどこにつながっているんだろうね?」って言う話をしたり・・・そういう考え方かな。
思考のバランス的には、自分としては良くなったんじゃないかなって。 - 城田
- そうですね。
偏らない感じですよね。チャンキングをうまく利用して、視点が変わるっていうこと? - 中野
- そうですね。
そういうことが『わかって』できるようになった。 - 城田
- なるほど。意識してやるっていうことですね。
それは大きな違いですね。
何となくそうなったのではなくて、チャンクの大小を意識してコントロールしながら、コミュニケーションをとるようになった・・・そんなところが変わったんですね。 - 中野
- そうそう。
そして・・・これはね、NLP(注:神経言語プログラミングという心理学)の影響があると思うんですけど・・・感情のバランスを保つということが、要は内側のコントロール、というのかな。ステイト・マネジメントですね。それが、うまくなったというか・・・ - 城田
- 具体的にはどういうことですか?
- 中野
- 具体的には今、この・・・去年の11月から、どっぷりと新しい仕事をやっていて・・・
- 城田
- ああ、新しい職場になったんでしたね
- 中野
- うまく行かないんですよ(笑)
- 城田
- 今までと違う環境ですしね。
- 中野
- やっぱり、そういうときって、落ち込むじゃないですか。
- 城田
- 落ち込むよねぇ。。。
落ち込みたくなくても、落ち込むよね。 - 中野
- そうなんです。
そしてそういった落ち込んだ自分でいると、それって・・・伝播するんですよ。周りに。 - 城田
- ああ、あれ怖いね。
- 中野
- みんなも元気なくなったり、職場の雰囲気が悪くなる・・・ていうのもあって・・・なかなか難しいんですけど、できるだけ・・・その今の状態っていうのを、「肯定的に見たらどう見えるか?」というふうに、考えてみて、内面の感情を、否定的なところからゼロベースまで、持っていく・・・っていうんですかね、持っていくようにしている・・・
- 城田
- なるほどぉ。。。
ニュートラルな地点にね。 - 中野
- そうそう。ニュートラル・ゾーンまでね。
なかなかハイなところまではいかないので、ニュートラルなところまでいくように。 - 城田
- そんなことができるようになったんですね。
それが変化ですね。 - 中野
- そうですね。
あとは、ですね。これは、あの、今の話につながるんですけど、物事を肯定的に考えるようにしている。
まあ、弱みの裏返しは強みだって、言い方もあると思うんですけど。物事を否定的に見るんではなくて、その裏返し、肯定的に見たら、どんな状況なんだろう・・・って否定的に考えるのではなくて、肯定的に考えて物事を進めていく。そういうことは、多くなりましたね。
会話も、肯定的な言葉を使う・・・ことが多くなった。 - 城田
- へえ。。。
それは職場にとってもいいですね。 - 中野
- そうですよね。
- 城田
- 否定的な言葉ばかりを使う上司よりも、肯定的で希望のあるコミュニケーションをする上司の方が、ただ話していたって、いいですものねぇ。
- 中野
- そうですよね。
今なんて特に・・・否定的というか、特に自分が何気なく使っている言葉では、「難しいよな、これって」という言葉をよく使っているんですよ。自分自身。
それで気づくんですよ。「あぁ・・・俺、むずかしいと、思っているんだ」って。だから目の前に課題があっても、なかなか手を付けられないんですよ。あるいは・・・進まない。そういうふうに思っているんだなぁって、そういう状況だと理解してるんだなぁってわかるわけですよね。 - 城田
- そうですか。。。
「これって難しいな」って言う言葉を自分が使っていることに、自分で気がついたんですね。
これを、さっきの肯定的な観方で言うと、中野さん的にはどんなふうになるの? - 中野
- そうですね、とりあえず、課題全体は難しいかもしれないけど、課題を細分化して一個ずつ、完了していこうかなって。一個ずつステップを踏んでいこうかなって。
- 城田
- なるほどぉ・・・
- 中野
- 全部をクリアするのは、むずかしいかもしれないけど、一個一個理解していけば、一個一個完了していけば・・・そういうふうに観方を変えると、「じゃ、一個進もうか」っていうようになるわけです。
- 城田
- そうですね。
- 中野
- なるべく、そういうふうにしてますね。
- 城田
- それもまた、中野さんに起こった変化ですね。
- 中野
- そうですね。そんなところかなぁ。
- 城田
- さっき、コーチングを始めて、周りの人や、コーチングをした相手の人も、変わったって言ってたけど、そのあたりは・・・?
- 中野
- はい、ひとつは・・・実際に会社から、コーチングを学びに行ってこいって言われて、勉強させてもらって、それで、社内のマネジメント層にコーチングのスキルを紹介して、使えるようになってもらって・・・っていう課題があったわけですけど。
そして、会社の中で、全課長に対して、コーチング研修をやったんですよね。
で・・・どのタイミングで聞いたのか、忘れたんですけど・・・以前は人事の方に、社員から結構クレームが入っていたりしてたんですよ。「上司が話を聴いてくれない」とか・・・ - 城田
- ああ・・・よくあるクレームですよねぇ。
- 中野
- そう、ちゃんと面談してくれないとかね。
それで、そういうクレームが減ったっていう効果が、あったんですよ。 - 城田
- すごい。
それは・・・定量的な成果ですねぇ。 - 中野
- はい(笑)。
「最近なくなったよね。そう言うことって」って。
それがすべてではないにしても、効果としては、少なくても、あったんじゃないかなって思いますね。 - 城田
- 影響があったんでしょうね。
- 中野
- そう。効果が出てよかったなと思って。嬉しかったし。
会社の中で起こった管理職の変化ですね。 - 城田
- 会社も嬉しいですね。
- 中野
- ええ、会社も嬉しかったと思います。
- 城田
- いいですよね。コーチングって。
今の話もそうですが、中野さんが最近コーチングを使って、機能したなって思ったことがあったら何でも教えてください。 - 中野
- はい。
結構・・・長い期間・・・1年くらい、かかったと思うんですけども・・・あるひとりの部下がいて、まあ、タイプで言えば・・・ディレクターなんですね。 - 城田
- ああ・・・成果を重視するタイプ、ですね。
- 中野
- はい。
周りのことを気にするよりも、自分が求めている成果を優先する・・・その部下の方向性に合わないことっていうのは、要は、否定的なんですよね、どうしても。 - 城田
- その人が、否定的になっちゃうってこと?
- 中野
- ええ、そう。
例えばその部下と、協力して仕事をしようとする相手に対して・・・相手の考えが自分がやりたい方向でない場合に、観方がどうしても自分本位のみになってしまう。「私はこう。こっちの方に進みたいんだ」っていうことが強い部下だったんですよ。
それを・・・コーチングスキルを使いながら、「相手はどう思うんだろうね?」「こういう観方をしたら、どうなんだろうね?」っていうことで、いつもその、その人が観ている視点を変えてあげるような質問をしていったことによって・・・1年後だったか・・・よく憶えてませんが、いろんな視点から、観られるようになってきましたね。 - 城田
- へえぇ。。。
その人、成長したんですね。 - 中野
- ええ、成長したと思いますね。
- 城田
- でも、1年間ずっと、根気よく、その部下に問いかけ、関わり続けたんですよね。そうしたら、成長した部下がいた・・・
- 中野
- そうですね。
あの・・・すごく、勿体ないって、思ったんですよ。 - 城田
- ディレクタータイプの人って、優秀な人、多いですからね。
聞いただけでも、その人、すごく優秀そうですものね。 - 中野
- そうですね。
やっぱりディレクタータイプって、成果重視、結果重視でいるので、ぐいぐい引っ張っていけるし、会社にとってはすごく大事な人材なんですよね。
その人は、若かったので、これからリーダークラスに、あるいは管理職クラスに行けると、思っていたので・・・そして、上に進んでいくにあたって周り・・・メンバーとか、他の部署の人たちとか、自分が相手をする人たちの考え方、物の観方を理解したうえで、一緒になって進んで行くっていうことが、できないと・・・ひとりよがりのね、そうなっちゃうなって思ったので・・・
それで根気よく・・・ - 城田
- その部下の方も成長があってすごくよかったですね。
- 中野
- ええ。
たまたま、採用教育課っていうところにいて、私がコーチの勉強をしたきた、ということもあるので、当時の部下のふたりを同じように、学ばせに行ったんですよ。 - 城田
- コーチングの勉強をしてもらいに?
- 中野
- そうそう。
部下本人も学びに行ってみて、相手と相対してみて、いろんな人と関わって・・・っていうのを経験しながら・・・そして、私が問いかけながらだったので、学びながら・・・だったから、ということもあったかもしれない。 - 城田
- なるほど。
双方向からいい効果があったんですね。 - 中野
- そう。
- 城田
- それは上司にとって、すごく嬉しいことですね。
- 中野
- そうですね。。。
これまでは自分のやり方がすべていいと、思っていただろうし、それで合わなければ、ぷいっと、ってそんな感じでしたね。
それが違う意見の人に対しても、ちゃんと受け止めて、それから対応できるようになったと思うし。 - 城田
- 人ってそんなに変わるんですね。
- 中野
- 変わりますよ。
- 城田
- そうね。
- 中野
- ただ、根本は変わらないですよ。
- 城田
- もちろん、そうよね。
根本は個性だから。 - 中野
- それはそれでいいじゃないって言っているんですけど。
観方とか考え方とかが、変えられればね。 - 城田
- 対応できるようになった・・・ってことかしらね。
- 中野
- そうそう。
- 城田
- 今のが、コーチングが機能した、というお話ですね。
- 中野
- ええ。
- 城田
- 今、視点を変えるって言っていたんですけど、その他に、その人に対して意識してやったこと、工夫したこととかって、どんなことですか?
- 中野
- そうですね、あの、よくご存じだと思うんですが、まず相手を受け止めてあげることですね。
ペーシングをしながら、相手の考え方を私がまずいったん、受け入れてあげる、よく聴いてあげる、そしえ、その後で・・・ですよね。
あとで、フレームを変えるっていうか、あるいは視点を変えるっていうか、知覚位置を変えるというか・・・「相手から今のあなたを見たら、どう見えるのかな」というようなことで、特に視点を変えてあげたほうがいいですね。 - 城田
- それもちゃんとしっかり、相手を十分受け止めてからだ、ということですね。
それがなくて視点を変えるような質問をしても、結構相手には抵抗があったりするじゃないですか。質問をしたとたんに遮断してしまったり。
だからよっぽど下地作りをきちんとしないとうまくいかないと思うんですが、今のお話では、中野さんはずいぶん、ていねいに下地作りをされたんじゃないですか。 - 中野
- ええ。
相手の話を本当に傾聴して、「わかるよ」「わかるよ」って。「やりたいことはわかるよ」「それもいい方法だと思うよ」って受け止めておいて・・・「こういう視点から見たらどうだろう?」ということで、相手の話を受け止めてから、視点を変えてあげた・・・というか、投げかけてあげたことがよかったのかな。 - 城田
- そのとき、中野さんはどんな気持ちで相手を受け止めていたの?
- 中野
- ですから、本当に、一生懸命・・・もう私の頭の中では、多分、視点を変える質問を考えながら、だったと思うんですけれど、それはできるだけ見せないように、本当に承認をして・・・ということに気を付けていましたね。
- 城田
- 大変なことですよね。
明らかに「それはちょっとまずいんじゃない?」っていう考えを主張している人を、全面的に受け入れるっていうことは、本当にむずかしいことですよね。ましてや上司という立場だったら、よけいしづらい部分ってあるでしょう。
かなりの辛抱強さが必要ですね。 - 中野
- そうですね・・・
あの、これってペーシングっていうのかどうか、わからないんですけど、相手には・・・こう、激論じゃないんですけど、すごく、内面で葛藤が起きていると、がーって言ってくることもあるじゃないですか。
そういうときはそれにつきあってあげるのも、いいかなって思ってやったこともあります。 - 城田
- なるほどねぇ。。。
- 中野
- 言い合いしてあげる。
- 城田
- うん。ペーシングだと思う。
逆に、冷やや~かにしていたら、むかっとくるかもね。 - 中野
- そう。「自分が、こんなに話しているのに、なにしらっと聞いているんだろう・・」とかね。
そういうときには、こっちも、反対意見も言ってあげたりとかしながら感情と感情のぶつかり合いをそこで、一回やっておいて・・・っていうこともやりましたね。 - 城田
- へえぇ・・・
- 中野
- あえて戦っちゃう。
- 城田
- それもいい方法だと思う。
- 中野
- ずっとそういうエネルギーレベルでいるのは、人間ってむずかしいんで、いったん燃え上がって、それで冷めてきたときに、そのときに質問を投げかけてあげるのが、いいのかな・・・っていう感じですよね。
- 城田
- そんなペーシング、素晴らしいですね。
- 中野
- それもありだなって思ったんですよ。
- 城田
- 向こうが舞いあがっているのに、こちらも舞い上がらないと、気持ちが離れちゃうものね。
- 中野
- エネルギーレベルに差がありすぎちゃうと思うんですよね。
- 城田
- へえ。
エネルギーのペーシング、中野式ですね! - 中野
- いえいえ(笑)
- 城田
- さて、ペーシングというスキルが、今話題になりましたが、中野さんが考える、コーチに求められる、すごく重要なスキル、あるいは考え方のようなものでもいいのですが、大切なものって何ですか?
- 中野
- はい。
あの・・・ひとつは・・・これはスキルということではなくて、人を見るときの人間観っていうんですかね・・・ - 城田
- 人間観、ですか?
- 中野
- 我々で言うところの前提ってことだと思います。
やっぱり、私と対面しているその人には、何かを達成したり、成長したりするためのリソースは必ず、彼等、相手の中にあるんだっていうところから、出発する、という・・・その人間観に立って、部下とかクライアントに対して、コーチとして・・・まあ、子供に対してもそうだと思うし、そういうところからスタートする・・・それをしっかり持っていることが、大事なんじゃないかなって、まず最初にそう思っているんですよね。 - 城田
- 同感です。まったく、同感です。
それがなきゃあね、その後の話は、何も意味がないよね。 - 中野
- そうそう。
だから、会社の中で「あいつ、できないやつだから」って言う人たちがいるじゃないですか。
ま、たしかに一面から見たら、そうかもしれないけれど・・・ - 城田
- そうよね。「今は」とか・・・
- 中野
- そう。「このことについては」とかね。
たとえば「企画提案については」とか「プレゼンテーション」については、とかはそうかもしれないけれど。 - 城田
- 部分的なものについて、ですよね。
- 中野
- そうです。それを、人間として・・・みたいに、すごく大きなチャンクで決めてしまうのはどうかと思いますね。
ある1個のスキルだけ、仕事だけであって、全否定ではないと思うんですよ。
でもなんか会話していて、全否定に聞こえる。「それはおかしいよな」って思っていて。 - 城田
- おかしいよね。
悲しいよね。 - 中野
- そう、悲しい。
そうではなくて、やっぱり前提としては、ちゃんとリソースは持っているんだっていうところからスタートするってことが必要かなって思っています。
そしてさらに・・・ですね、観察する力。 - 城田
- いいこと言いますねぇ・・・
- 中野
- いや・・・
これもまたNLPが影響しているかもしれないけど、人間っていうのは、内側で起こっていることは表情や、態度とか、声のトーンとか、いろんなところに表出されてくるっていうことを、コーチは、しっかりと観察をして受け取って、それをフィードバックする・・・そうする必要があると思うんですよ。相手をみながらコーチングをしないと。観察力ってすごく重要だと思うんですよ。
コーチングって何のためにやっているかって言うと・・・例えばセッションをして、終わった後に、クライアントが実際にコーチに約束したことを実行して、クライアント自身が成果を創ってくることが、それがコーチングの目的ですよね。
そのときセッションの中で、クライアントが言ってることは、表出していることと一致しているのか、っていうことを、コーチはしっかり、見ていなければいけないですよね。
「本当に腹くくって、約束してねぇな」っていうとき、あると思うんですよ。「できない」と思っているのに、口では「やっていきます」って言っている場合があると思います。でも表出している表情とか、あるいは声のトーンとかが自信なさそうだったりしたら、そのときはもう一回、コーチは問いかける必要がありますよね。「本当にやろうって、本当に思ってる?」って。 - 城田
- そうですねぇ。
特に上司と部下のときなんて、気をつけなくてはならないですね。
よく上司だけが燃えていて、「目標はこれだ!やるぞ!」と言って、部下も「やります」と言っているけど、実は部下の方はそうではない・・・ってそんなことよくありますよね。 - 中野
- 多いですね。
- 城田
- それを、じっくり観察して、部下の真意をたしかめるわけですね。
- 中野
- そうです。
観察する必要があります。 - 城田
- それが大事なんですね。
- 中野
- そうですね。そして、特に最近思うのは、承認する力。
自分も今、ひしひしと感じているんですけど。
自分では一生懸命やってるのにって思っているわけですよ、できなくてもね。
ですから、特に他人から承認されることがなくても「まあ何とかやってるよな」って自分で自分を認めながらやっているんですけど・・・やっぱりね、人からね、例えば、「ごくろうさん、ごくろうさん」だけでも、いいんですよ。会議が終わって、そこで立てた議題について承認とかが
得られた場合には、戻ったときに上司から「ごくろうさん、ごくろうさん」って言われるだけでも「ああ、やってよかったな」って思うわけじゃないですか。
人はやっぱり人から認められるとか、見ていてもらっているとか、見守ってもらっているとか、そういうことを受けると、それってモチベーションにつながると思うんですよね。 - 城田
- すごくつながると思います。
- 中野
- モチベーションがないと、人ってなかなか動けないと思うんですよ。
ですから、人をモチベートしてあげる、っていうこともコーチには、必要なスキルだと思います。 - 城田
- 上司だったらなおさら、ですよ。
- 中野
- うん、なおさら。
それから、「ありがとう」って言う言葉もすごく重要だと思うんですけれども・・・
何か部下に頼んで、やってもらったときや提出されたものに対しても「ありがとう」っていうことで受け取って、「お疲れさま」っていうことで受け取って、ということをできるだけやろうとしています。
まあ、承認する・・・ことで、次の仕事へのエネルギーやモチベーションにつながるようにする、ということがコーチとして必要かな。 - 城田
- 大切なことですよね。
- 中野
- そう思います。
- 城田
- すべては、やる気で、できあがっているようなものですものね。
- 中野
- そうです。
- 城田
- さて、コーチにとって大切なこととして、相手にリソースがあるという前提から入る、観察して相手をよく見極める、そして承認をする、と出てきましたね。中野さんのコーチングへの思いがよくわかったような気がします。
それで、中野さんにとってとても大切であるコーチングを使って、これから社会で・・・ここからチャンク大きいですよ(笑)、実現したいことを教えてください。 - 中野
- はい。
さきほどもちょっと話したんですけど、何のためにコーチングを使っているのかっていうと、そのセッションあるいはその会話を通じて、その人たちが違いを創ったり、成果を創ったり、課題を解決したり、目標を達成したりっていうことに、つながるために、やっているわけですよね。
そして、そういうことをしていくことで、人は成長をしていく・・・わけですよね。
そう言う人たちを、コーチングというものを使って支援していくことで、その成果を創ったり、違いを創ったりする人たちっていうのは、どういう状態になるのかっていうと、毎日、わくわく、いきいきとね、肯定的に、日々、暮らしていける、というのかな。 - 城田
- そりゃあ、そうですよね。
やることがどれもうまくいくのだから、毎日楽しくて、わくわくするのは決まってますよね。 - 中野
- そうですね。ですからコーチングを通じて、そういう人たちを、たくさん、生み出していく・・・そういうことをやっていきたい。そういうことで社会に貢献するというのかな。
そういうのがひとつ・・・ですし・・・ - 城田
- はい。
- 中野
- そしてもうひとつは・・・
今ね、チームをね、創りたいと、思っているんですよ。 - 城田
- チームを、創りたい・・・?
- 中野
- ビジョンを実現するチームを、目標を必ず達成するチームを、創る。そういったことをやっていきたいって思っているんです。
これは「チームコーチング」というものを使うんですけれども・・・
まとめると、チームコーチングの普及とか実践とか、研究開発ということを通じて、人と組織と社会を元気にするチームを、世の中にたくさん生み出していく、ということで、社会に貢献する、ということですね。
そういうことをもうひとつ考えているということです。 - 城田
- それは社会的にとても意義のあることじゃないかしら。
だってほとんど人ってチームで動くわけでしょう。ひとりでやっていることなんてほとんどないですものね。
ビジョンを実現するチームを世の中にたくさんつくりたい、ということでしたが、具体的にはどんなふうに、今進んでいるんですか? - 中野
- はい。
あの・・・昨年京都で、第1回目のチームコーチングカンファレンスというものを開催してですね、私たちが学んできたチームコーチングというものが、どういうものなのかっていうことを世の中に知って頂こうという機会をつくって、お互いに学びを深めていきましょうという、企画をやりました。104名の方にご参加いただきました。
そして第2回目を、今度は東京で、今年の10月に開催する運びとなってですね・・・そして、この1年間活動してきて、事例も多く出てきたので・・・ - 城田
- 活動っていうのは、今中野さんが一緒にやっている仲間と、事例ができたっっていうこと?
- 中野
- そうですね。仲間と一緒に創った事例と仲間がそれぞれ創った、という事例ですね。
紹介できる事例が多くなってきました。 - 城田
- つまり生の話ね。
- 中野
- そう、生の話です。
で、どちらかというと、通常のカンファレンスというのは実践した側の、やった側の話って多いと思うんですけど、私たちのカンファレンスでは実際にチームコーチングというものを受けてみて、変化した人たちの生の声を、聞いてもらおうと思って・・・ - 城田
- えっ? そんなのがあるの?
- 中野
- はい。
- 城田
- わぁ、それは面白い!
すごく聞きたい! - 中野
- ええ、そこもひとつ新しい試みとして、やった側だけでなく、受けた側の人たちが、実際どういうふうになったのか、さっきの質問じゃないですけど、前後で変化があったのかっていうことも、ひとつ聴いていただければなと、いうことで企画をいれてあります。
- 城田
- それ、すごく興味ある。
- 中野
- そうですか、ありがとうございます。
そういった活動を年一回やりながら、ビジョンを実現するチームを、成果や結果を創っていくチームを創る、そういうものを創りだし続けていくチームコーチングという概念を、世の中に知って頂きたいですし、そういうチームをたくさん生みだしていきたい、ということで、今、年一回、やっています。 - 城田
- 今年の10月3日?
- 中野
- はい。
- 城田
- 第2回目、ですね。
- 中野
- はい。
- 城田
- ちょっと気が早いんですが、第3回目、とかあるんですか?
- 中野
- あの・・・第3回目も案があって・・・ごろがいいといいますか、数字の並びがいいので、2010年の10月10日くらいにやりたいねっていう話が出ています(笑)。
- 城田
- それはいいですね!
この活動が広まったら、どんなふうになるんでしょうね。 - 中野
- そうですね。
人が集まればグループになるだけですけど、グループとチームの違いって、すごく大きいって、私たちは思っていて、単なるグループからチームになるには、どういったことが必要なのかっていうことも含めて、知っていただけると思いますし、じゃあ、もっとも効果的なチームってどういうチームを言うんだろう・・・そういったこともお伝えできると思います。
そういったことを通じて、世の中にたくさんの「効果的なチーム」ができると思います。 - 城田
- 私も是非、行きたいと思います。
- 中野
- ありがとうございます。
- 城田
- さて、インタビューもそろそろ、終りの方に近づいてきました。
いいお話をたくさん聴きました。
最後に、これからコーチングを受けてみたい、と言う人に何かメッセージをお願いします。 - 中野
- はい。是非、お勧めします。
私も実際、コーチングを受ける体験もしていますけど、実際にコーチに質問してもらって、自分の考えを言葉に出して言って、ですね、そのことをコーチが繰りかえして言ってくれる・・・結果として、2回、自分の耳で聞いている訳ですね。
ということは、自分の考えていることを言葉に出すことによって、その言葉をまず自分の耳で聞いて、そしてコーチの口からも聞いて・・・考えていたことをより理解することになると思うんですよ。「あ、今俺ってこういうふうに思っているんだ」とか「なるほどね」っていう体験ができると思うんですよ。
で、そこからがスタートだと、思うんですよね。
だいたいその、もやもや感が内面にあって、今どういう状況にあるのかってわからないのに、目指そうとしている方向を目指したって、ギャップがわからない・・・っていうことだと思うんですよね。 - 城田
- なるほど、そうですよね。
今の自分もわかっていないわけだものね。 - 中野
- そうそう。
現状を把握する、今の自分を理解する、ということに対して、まずコーチングは機能する、と思います。「今の俺ってどうなんだろう?」ってね、そこから始まるんだと思うんですよ。
自分の方向性を決めたいなって思っている人なんかは、すごくいいと思うんです。だからおススメ。 - 城田
- 自分で話して、コーチに繰り返してもらって、自分の耳で聞いて、言葉で感じて、そうして自分自身が定まっていくのでしょうね。
- 中野
- そうそう。
自分自身はこう思って、理解しているんだ、考えているんだ、ということを、ちゃんと言葉で引き出して聞くことによって、よく理解できると思うんですよね。おススメです。 - 城田
- では、今度は、クライアントではなくて、自分がコーチングを学んでみたい、と言う人にメッセージを。
- 中野
- これもお勧めです(笑)。
人と関わる、ということが仕事においてまずひとつ、必ずあることですよね。そうしたときに、コーチングってコミュニケーションのスキルになりますので、そのスキルを高めておいて、損はないと思うんですね。
それは、コーチングを学ぶことによって、コミュニケーションのスキルってあがってきますので、特に聴いたり、承認したりすることを通じて、コミュニケーションのスキルがあがってきますから、そういう点では・・・特に企業人なんかは学んだほうがいいんじゃないかなって思いますし・・・部下とか、あるいは人を支援するっていうことに使っていくわけですけど、自分に問いかけて自分で答えを出すっていう、セルフ・コーチングもできるようになるわけです。だから自分の目標達成とか課題解決とか、技能とかスキルとか知識とかを向上するのに、まあ、実際はコーチとやった方がいいと思いますけど、単純に言えば、自分に訊いて、自分で答えを出す、ということができるようになりますから。
そう言う意味では成長したいとか、成果を出したいと思っている人なんかには、このコーチングのスキルを学んだら、いいと思いますし、管理職クラスを目指す人は、特に聴く力を鍛える、と言う意味では、やっておいた方がいいのではないかなと。
世の中のリーダーたちは、聴くのが上手だと言いますよね。
コミュニケーション・スキルを高めておいて損はないと思いますよ。 - 城田
- ひとつ訊いてもいい?
コミュニケーション研修とかもあるじゃない?
コーチング研修と、それと・・・どっちに行ったらいいと思う? - 中野
- 結構いい質問ですね、それは。・・・難しいな。
さっきも、ちょっと話したんですけど、コーチングの結果と言うのは、やっぱり成果とか、プロセスもあるんですが、プロセスを含んだ成果とか、結果を出すことにつながることをやっていると思うんですね。成果とか結果につなげていくって言う意味ではコーチングの方がいいんではないかな。
コーチングの中に、コミュニケーションのスキル・・・聴くとか、承認するとか、が含まれていると思うんですよ。
コーチングの概念が大きくあって、それがクライアントや部下の、成果や結果につながっていくことを、支援するスキルになると思うので、コミュニケーションの研修ととコーチングの研修でどっちに行ったらいいのかって言ったら、成果をつくるならコーチングに行ったほうがいいですね。 - 城田
- 特にビジネスマンはそうね。
- 中野
- そうですね。
コミュニケーションのスキルというのは、しっかりと聴いてあげるとか、相手を受け止めてあげることとかであると、思うんですけど。 - 城田
- なるほど。
成果っていうのはまた別なのね。 - 中野
- 別の話になってくると思いますね。
コミュニケーション研修は、アサーションとか傾聴とか、が中心だと思うんですよね。それに比べてコーチングはより成果志向なんだと思います。問題解決とかも含まれていると思います。
ビジネスマンにとっては、コーチングがいいですし、自分の成長を願っている人にも、特にいいでしょうね。 - 城田
- 結果を出せるんだものね。
- 中野
- そうですね。
- 城田
- さて、これで質問はすべてですが、何か言い足りなかったこととかは何かありませんか?
- 中野
- いや・・・すごく、たくさん話させて頂いたと思います。
- 城田
- そう? あっという間でしたけど。
- 中野
- ええ、あっという間でしたね。
・・・なんか・・・よかったですね。
やっぱり、話をして。自分で話をしていて、さっきの話じゃないんですけど、自分の話を自分で聞いていて・・・今の現状って、状態としてはあまりよくない状態ではあるんですけど・・・ - 城田
- うん。忙しい・・・
- 中野
- そう。でもそれってコーチング使ってみたら、いいよねって言うように・・・「なんでこんなこと、忘れてんだろう」って思ったり(笑)。そんなことを感じましたね。
自分でコーチングやればいいやって。 - 城田
- そうですね。
長いお時間、インタビューにご協力下さり、本当にどうもありがとうございました。 - 中野
- ありがとうございました。